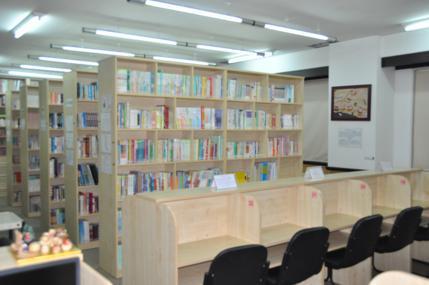清水武則前モンゴル駐箚特命全権大使は現在は日本の中央大学において国際関係およびモンゴルの歴史文化、政治、経済発展の授業を担当し、学生とともに「モンゴルの経済発展:モンゴルにおける観光業の発展」というテーマで研究を行っている。
昨年9月にゼミ生を引率してモンゴルを訪問、テレルジ、ハルホリン、ウギー湖などでツーリスト向け宿泊施設を訪れ、日本人から見てどのような問題があるのか、何が改善されたかを調査し、さらなる改善ポイントについて検討したという。
この調査報告は現在準備中であり、今年は再び6名のゼミ学生を伴いモンゴルを訪問、土産物の調査を実施した。以前のインタビューで、清水氏は適切な観光政策があればモンゴル人は夏に働き、冬に休むことができるようになると述べていたが、今夏の調査について聞いた。
モンゴルの製品をどこで買えばよいのか、整備された情報がない
Q. ようこそモンゴルにいらっしゃいました。今回の調査について教えて下さい。
昨年は学生を連れて地方を旅行するとともに、博物館・美術館めぐりを行い、どのような問題があるのか、何を改善すれば観光分野の発展を支えることができるのか、という観点から調査を行い、帰国後に学生たちは調査レポートを作成しました。
今年は土産物を中心に調査することにしました。モンゴルで製造されている製品や土産物は多くありますが、果たしてどのようなものが外国人旅行者とりわけ日本人に興味を持たれるのかにに注目したのです。
モンゴルの店には実に多くの種類の商品・製品が並んでいますが、外国人旅行者の関心を引くものは多くありません。観光客はしばしば「買うものがないなあ」といって店を後にしていきます。観光という分野は宿泊施設、土産物、飲食といった多くの面で経済に正の影響を与えるますが、残念ながら、モンゴルの製造者や販売者は観光客の関心を理解するために必要な調査を行っていないようです。そのため、私たちはこの面から主に調査を行うことにした。
Q.以前に比べるとモンゴル産の製品、なかでも土産物の種類や数は増えています。土産物の調査をどこで主に行ったのでしょう。
まず、どこでどのようなモンゴル製品を買えるのか、その情報がオープンでないことに問題があるとみられます。どこで何を購入できるのか、その情報が観光客にとっては決してわかりやすいものではありません。わたしたちは国立デパート、メルクーリ市場、シャングリラ・モール、市内大通りに面する「Made in Mongolia」を看板に掲げる店に行きました。学生たちは、モンゴル国立大学とハンガイ大学のモンゴル人学生たちと共同で調査を行いました。
Q.日本の若者たちがモンゴルで気に入った製品は何だったのでしょう?
若者たちが自身の眼で見て何に興味を持つのか私も知りたかったので、私は彼らに同行せず、学生たちだけで店に行ってもらいました。
学生の一人はHuurug(嗅ぎタバコ入れ)を気に入ったようでしたが、その製品がモンゴル製なのかどうかはちょっと確信が持てないですね。また、”Buramkhan”の飴、「Zoson」、「Goo」、「Lhamour」の製品、切手、岩塩で作った土産物、小さい馬頭琴、コーヒーの紙コップに似顔絵を描くサービスなどが気に入ったと言っていました。私はあまり聞いたことのないブランド名もありましたね。

学生たちによれば、お土産物を手にとってもモンゴル産の製品なのか外国産の製品なのかを区別できないことがあると言っていました。一人の学生はロシア産の飴をモンゴル産と思って買ってきていました。ともあれ、若い学生たちの関心を引く商品やサービスがあるということはわかりました。
岩塩で作った土産物といえば、面白いことに日本人は岩塩をとても好みます。私が若いころモンゴルからの土産物を見つけることができずにいたとき、運良く岩塩を手に入れ、スーツケースいっぱいに買って帰ったことがあります。日本には岩塩がありません。空港に到着すると日本の税関の職員に「なぜこんなにたくさんの石を持ち帰っているのですか」と聞かれました。私は「石ではなくてこれは塩です」と答え、税関職員と30分近くも塩だの石だの問答になったことがありました。当時日本では岩塩はあまり知られていなかったのです。
最近のモンゴル産の岩塩製品は当時に比べずっと美しい細工が施されています。日本人はモンゴルの岩塩の質を高く評価し、複数の企業が買い付けています。昨年に私の母が亡くなったのですが、日本では故人が亡くなってから1年後の命日に一周忌として知人を招いて法要を行います。私は参列者に対して御礼としてモンゴル産の岩塩と蜂蜜を贈りました。参列者はどなたもたいへんに喜んでくださいました。なかには塩飴もあって、日本の夏の暑さに塩飴はとてもよいのでわざわざ注文する人もいて、私はとても嬉しく思っています。

旅行者の関心を集める観光地のインフラに注意を向け、早期に改善する必要がある
Q.学生たちと田舎にも行かれたのでしょうか。昨年モンゴルを訪れたNISHINO Kurumiさんは星空の写真を撮ってとても満足していましたね。
私たちはウムヌゴビに旅行しました。残念ながら曇りの日が続き、学生は念願の写真を撮ることができませんでしたが、バヤンザグに行ってとても喜んでいました。ゴビでは古いツーリストキャンプに宿泊しました。また、新しくできたキャンプも含め周辺のツーリストキャンプをいくつか訪れました。
学生たちは日本からモンゴルにやってきて、ウランバートルを見ても「モ ゴルに来た」という思いは浮かばなかったと言っていました。田舎に来て、ゴビに来て、広がる草原を見てはじめて「本当のモンゴルにやってきた」、自分たちの想像していたモンゴルはこれだと感じたのです。素晴らしい体験をしましたが、大変なこともありました。たとえば、宿泊先のゲルでは夜になるとネズミが走り回り、ひと晩中その音で女子学生たちは眠ることができなかったと言っていました。
日本人のなかでも若者たちの関心を引くものがモンゴルの田舎にはたくさんあります。そのため、地方で発展の必要のある事柄は多いでしょう。
Q.たとえば、最初に改善する必要のあることは何でしょうか?
私たちは昨年カラコルムとテレルジに行き、今年はゴビに行きました。外国人にとってはお手洗いが非常に重要なので設備の整ったトイレを備えることが大切です。宿泊施設の雰囲気や設備は良くなっているものの、インフラについてはまだまだです。道路の整備状況も良いとはいえず、かなり疲れます。私たちはゴビに行くのに8時間も車に揺られました。
一気にすべての問題を解決することはできないとしても、明確な方針を策定し、ウムヌゴビ県、フブスグル県、オブス県といった観光客の関心の高い地域のインフラに集中して早期改善すれば地方観光の発展の可能性も十分にあります。そのための政策が必要です。
現在、ウランバートルーナライハ間の道路が整備されています。整備が終了すればテレルジに行く人の数は増えることでしょう。観光客の関心を引くことができるか否かは多くの要素が絡みますが、そのなかでもインフラとサービスの質は決定的に重要です。
またサービスの文化や質が向上しているところも見られるものの、相変わらずのところもあります。日本には「おもてなし」という言葉があります。一期一会の精神で、サービスを提供する側はこのおもてなしを徹底します。日本のサービスがきわめて高いレベルであるのはこれに基づいています。
日本ではお客様は神様という考えがあるので、サービスに関する特別な教育を行います。従業員の考え方も異なります。従業員であっても、所属する会社のためにという意欲をもって全力で勤めます。けれどもモンゴルでは異なります。自分の会社ではないから商品が売れようが売れまいが関係ない。場合によっては自分の会社であっても自分は社長なんだからという向きもあります。社会主義時代には懸命に働かなくても同じだけの給料を貰えるといった考えが一方にありました。けれども、近年では改善されているところもあることも確かです。
Q.貴方は日本からモンゴルに来る観光客の数が増えないのは航空券の価格が関係していると以前指摘してましたが現状はいかがですか?
今回私たちはゴビで日本からやってきた一人の女性に出会いました。11年前にモンゴルに初めて訪れ、それ以来毎年モンゴルを旅行しているそうです。一緒に来ておられたご主人は数年前に亡くなられたそうですが、その後も続けてモンゴルにやってきているということでした。彼女の心を惹きつけたのは何だったのかと聞くと、モンゴルの平原が心から好きと答えてくれました。こうした人たちを増やすことが重要です。
航空券価格の問題は全く変わりがありません。学生たちのなかにも航空券の値段を理由に北京経由で来た者もいます。日本の航空会社が参入すれば競争が生じ、航空券の値段も下がると思います。今年は少し値段が下がりました。このこともあってか、日本からモンゴルに来た旅行者の数は増えているようです。この9月にモンゴルに来た日本人の数は減りましたが、私たちの搭乗した飛行機にはたくさんの日本人が乗っていました。モンゴルに対する関心は高まっているように思えます。
Q.日本の航空会社は、定期便の運行に明確な基準をおいていると聞きました。どのくらいの期間でこの基準を日本―モンゴル便が満たすと考えておられますか?
日本の航空会社は搭乗者数が100,000人以上の航路で定期便を運行します。50,000人で不チャーター便を就航し、これがその後に定期便になる可能性もあります。昨年は50,000人近くの搭乗者数でしたが、今年は50,000人に達すると思います。50,000人に達すれば、日本の航空会社の不定期便が就航し、数年後に100,000人に達すれば定期便が就航します。いまから5年後には100,000人に達するかもしれません。そうすると今後、1年間あたり登場者数を10,000人増やすには、日本からモンゴル、モンゴルから日本へと向かう人々を中国や韓国を経由せずに直行してもらうためにMIAT(モンゴル国際航空)のモンゴルー日本間の直行便の数を増やし、一定程度値下げを行う必要があります。日本から100,000人がモンゴルに来ればおよそ1億ドルがモンゴルに落ちることになります。
Q.日本の若者たちにモンゴルの情報を届け、両国の若者たちの交流を広げる、ということを貴方はよく述べておられますね。同行された学生の皆さんはモンゴルにもう一度来たいと思っていますか?

(学生)MACHIDA Yuki:学生のうちにはもう一度来るのは難しいでしょう。もっと安い値段でも東南アジアに行くことができ、モンゴルに来る費用だけで他のいくつかの国を見て回ることができるからです。卒業後にお金を貯めてモンゴルにくることがあるかもしれません。
(学生)ENOMOTO Rei:モンゴルは本当に素晴らしいところです。ただ、若者にとってはインターネットへの接続がとても重要なのですが、ネット環境はそれほどよくありませんでした。学生の間にはもう一度来ることはないと思いますが、またいつか必ず来たいと思います。
(学生)NABEMURA Kazuma:清水先生のゼミを受講していて、今回モンゴルに来ました。学生の間にまた来ることはできないでしょう。日本では地下鉄やバスなどに日本語、ハングル、中国語、英語での案内があります。モンゴルにはこうした外国人向けの案内があまりないので不便でした。また、日本の店では商品の値段や説明がすぐわかるよう記載されています。モンゴルではそうではありません。商品に値札や説明がないことがあり、モンゴル語がわからないので聞くこともできません。観光客には高い値段で売りつけようとしているのだろうか、と邪推してしまいます。このような基本的な要件を満たす場所はあまり多くありません。
他方、モンゴルの人たちはとてもよく肉を食べると聞いていたのでこちらでの食事を心配していましたが、嬉しいことに食事の選択肢は多かったです。現在のモンゴルの生活、食事について日本人はあまり知らないのではないかと思います。モンゴルでの食事について「どのような食事の習慣・主義をもつ方でもモンゴルに来て食事に困ることはありません」、という旅行者向けのメッセージが必要だと感じました。
学生たちが旅費が高いのでモンゴルにもう一度来ることはできないといっているのは残念なことです。けれども、問題は早晩解決すると思っています。私には故郷の大分県とモンゴルのあいだでチャーター便の就航というアイデアがあります。近年、静岡、福岡、北海道にチャーター便が飛びました。チャーター便の数が増えることは、両国間の観光分野の発展にとって重要です。
Q.観光情報が不足していることについて、貴方も学生さんたちも指摘しています。これも留意すべき問題のようですね。
そのとおりです。モンゴルに関する観光者向け情報を集約したポータルサイトがありません。旅行会社がこうしたサイトを作るのは難しいでしょう。国から協会等を通じて公式サイトを作ってモンゴルに関する情報を集約し、これをフェイスブック、ツイッター、インスタグラムといったSNSで周知広報する必要があります。これにはそれほどの費用はかからないでしょう。少ない費用で多くの人に情報を届けることにより、観光分野で勤める人びとを支援できます。このような投資を行うことは意義あることと思います。
たとえばシンガポールであれば、日本にシンガポール政府観光局の支局があります。日本も世界中に国を紹介する組織や施設を置いており、これに必要な多額の予算が用いられています。けれどもモンゴルでは、自然環境・観光省に観光を担当する部局はあるものの予算が少なく、十分な機能を果たすことが難しい状況です。
モンゴルの将来を考えると、観光分野は間違いなく重要です。貧困率を下げるうえでもこの分野が重要になります。昨年1,900万の日本人が海外旅行に行き、そのうち80万人がシンガポールへ行きました。そこで消費された費用はおよそ200億円にのぼると言われています。これら人たちのうち4分の1でもモンゴルに来れば、モンゴルは日本とモンゴル間の貿易赤字を観光で補うことができます。そのため、私たちは観光分野に注目し、調査を行っているのです。
私たちはこれから今年で2年目となる調査を行い、帰国後に調査をまとめて詳細な報告書を作成します。来年もモンゴルで調査を行い、その結果も含めて調査結果をまとめるつもりです。そして5年間教職をつとめ、その後に調査成果を書籍として発表する予定です。
仕事の成果についてお話しいただきありがとうございました。